発注点のあたりを付ける
先日、↓ を拝聴した。
www.youtube.com
恥ずかしながら私は今まで、指数分布というものを知らなかった。
なんて面白い!説明も超解り易い!!
そして思った。これって、発注起点を求めるのに使えないかと。

まず発注点とは、以下のサイトによれば
発注点とは、在庫が決まった数量になった時に、「補充せよ!」という指令を出す在庫量のことです。
と記されている。
shikumika.com
このように、発注点を求める方法は既に確立されており(?)新たな手法を
検討する余地はないかもしれない。
一方で2021年9月現在、半導体が入手困難のため、電子部品の発注リードタイムが
軒並み伸びている。このような状況下では一般的に、発注リードタイム長期化に
伴って、いつもより多めに在庫を確保しようとするだろう。しかし、過剰在庫は
避けたいところ。
そこで指数分布を用いて、発注点のあたりを付けられないかと考えたわけだ。
指数分布の定義は、上記You Tubeから引用すると以下のとおり。
単位時間あたり平均λ回起こる事象の発生間隔が、x単位時間である確率密度
注!ここから先は、私の思い付きです。数学的に正しくない恐れがあるため、「そんな考え方もあるか」ぐらいの参考意見にとどめおきください。
そこで、こんな風に考えた。
- ある部品について、昨年の使用回数(出庫実績)を集計する。
※使用総数ではないことに注意。 - 同様に、一回の最大使用個数を集計する。
- 指数分布から、「使用からn日以内にまた使用される確率」を求める。
- 上記確率から、n日以内に使用されるであろう最大個数を推測する。
- n日以内の推測使用個数とリードタイムから、発注点を求める。
例えば、こんな感じだ。
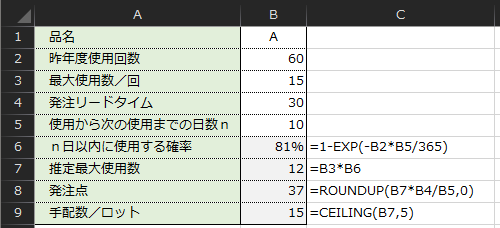
これによれば、在庫が37個を下回った時点で、15個を追加手配することになる。
また、半導体不足からリードタイムが120日になったとする。
この場合、30を120に変更することで、発注点は37個から146個へ変化する。

この考え方が有効か否か、生産管理担当経験の無い私には、判断しかねるところ。
使えるかどうか知り合い(生産管理部門員)に、それとなく訊いてみるとします。
参考まで。